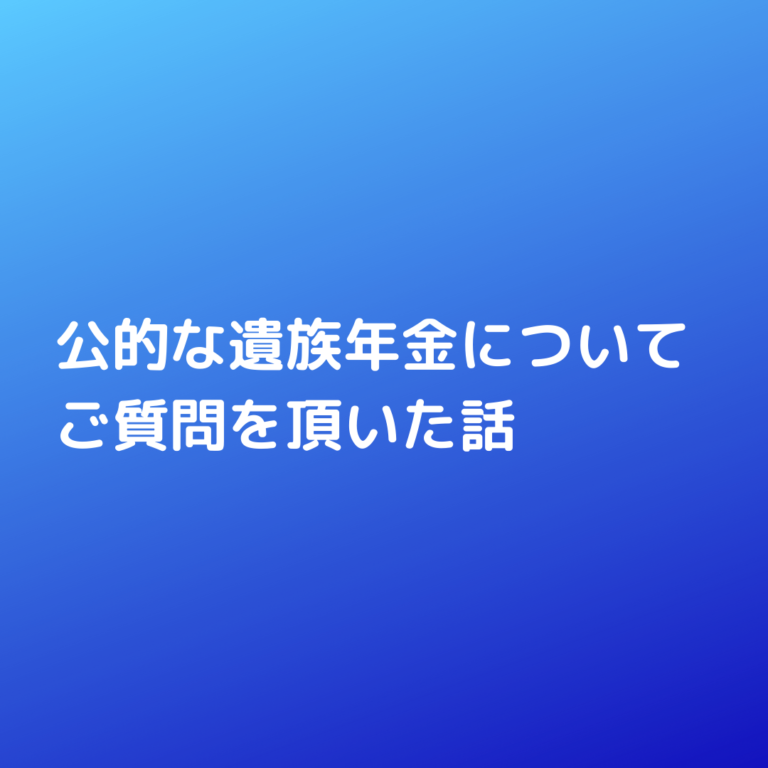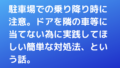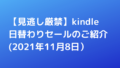遺族年金、遺族年金って言うけど、結局いくらもらえるの?という質問を頂きました。関連するものも含め、「いつ、どれくらい」をお伝えしていきたいと考えました。
今回は、世帯主がご主人である奥様からご質問を頂きましたので、そのケースでお答えします。できるだけわかりやすく簡潔にお伝えしたいと思います。
また、「公益社団法人 生命保険文化センター」のホームページがわかりやすいと感じましたので、目いっぱい参照しております。
ごあいさつ
こんにちは。
当ブログにお越し頂きましてありがとうございます。
お客様とお話をしていると、色々な話題を頂きます。出来るだけ頂いた質問にはわかりやすくお答え出来たら良いな、と考えています。こういう場で書き綴っていくことは、私にとっても良い影響がありそうな気がしますね。
とはいえ、基本的には同様の疑問を持っている方に、出来るだけわかりやすくお伝えできれば幸いかな、と考えております。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
万が一の際の「公的な遺族年金」には、ざっくりと分けると、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。この二つは、お亡くなりになられた方の職業によって分けられている、と考えて大まか間違いではありません。
自営業世帯と会社員・公務員世帯
よく「公的遺族年金は二階建て」という表現をされる方もいらっしゃいますが、この表現はわかりやすいかな、と思います。遺族基礎年金が一階、そしてその上の二階部分が遺族厚生年金、という具合です。
自営業世帯では、遺族基礎年金。
会社員・公務員世帯では、遺族基礎年金+遺族厚生年金。
ここもざっくりですが、そう考えていただいて大丈夫かと思います。
受け取れる年金
一階部分の基礎年金は、自営業世帯、会社員・公務員世帯、いずれも受け取れます。そして二階部分、厚生年金は会社員・公務員世帯が受け取ることが出来ます。
自営業世帯…遺族基礎年金(1階部分)
会社員・公務員世帯…遺族基礎年金(1階部分)・遺族厚生年金(2階部分)
受け取ることのできる人
自営業世帯
子どものいる妻・夫
子ども
※子どものいない妻・夫は受け取れない。
子どもがいる場合でも全員が18歳になった年度末。
この時期をもって受け取れなくなる。
会社員・公務員世帯
妻・夫・子ども
父母
孫
祖父母
※子どものいない妻・夫も受け取ることが出来る。
妻が年金を受け取るケース
自営業世帯…妻に子どもがいれば受け取ることが出来る。
会社員・公務員世帯…遺族基礎年金は自営業世帯と同じ、遺族厚生年金は子どもの有無に関係なく基本的には一生涯受け取れる(例外あり)。
妻に子どもがいる場合に受け取ることのできる額
子どもが3人の期間
自営業世帯…年額1,305,200円、月額108,766円(遺族基礎年金)
会社員・公務員世帯…年額1,819,455円、月額151,621円(遺族基礎年金+遺族厚生年金)
子どもが2人の期間
自営業世帯…年額 1,230,300 円、月額102,525円(遺族基礎年金)
会社員・公務員世帯…年額1,744,555円、月額145,380円(遺族基礎年金+遺族厚生年金)
子どもが1人の期間
自営業世帯…年額 1,005,600 円、月額83,800円(遺族基礎年金)
会社員・公務員世帯…年額1,519,855円、月額126,655円(遺族基礎年金+遺族厚生年金)
※子どもが18歳になった年の年度末で数には数えなくなります。
※例えば、長男19歳、次男16歳、三男12歳、の三兄弟の場合、実際の子どもの数は3人ですが、遺族年金の受給で言うと、子ども2人の期間を参照します。
※全員が18歳になった年の年度末を迎えた場合、子どもがいない妻と同じ扱いとなります。
子どものいない妻
妻が64歳未満の期間(夫死亡時に妻が40歳未満の場合)
自営業世帯…なし
会社員・公務員世帯…年額514,255円、月額91,633円(遺族厚生年金)
妻が64歳未満の期間(夫死亡時に妻が40歳~64歳の場合)
自営業世帯…なし
会社員・公務員世帯…年額1,09,955円、月額42,855円(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算)
妻が65歳以降の期間
自営業世帯…年額780,900円、月額65,075円(妻の老齢基礎年金)
会社員・公務員世帯…年額1,295,155円、月額107,930円(遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金)
※その他受け取る事のできる可能性のある給付もありますので詳細はこちらよりご確認下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
数字の羅列で読みにくい部分もあったかもしれませんね。
遺族基礎年金(国民年金)のみ加入の場合と、遺族厚生年金(厚生年金)も加入の場合とでは、受け取れる期間、金額が随分と違うことが見て取れたかと思います。
ご自身の家族構成と、加入している公的年金保険を確認し、世帯主の方の万が一がいつ起きたら、いくら、いつまで給付があるか、がわかってくると思います。
公的年金っていったい何?
いくらもらえるの?
という疑問の解決に、少しでもお役に立てれば幸甚です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※記事内の給付額等は記事作成時点のものです。
※あくまでも公的遺族年金の概要です。詳細は日本年金機構や 公益社団法人 生命保険文化センター 等のホームページをご確認下さい。