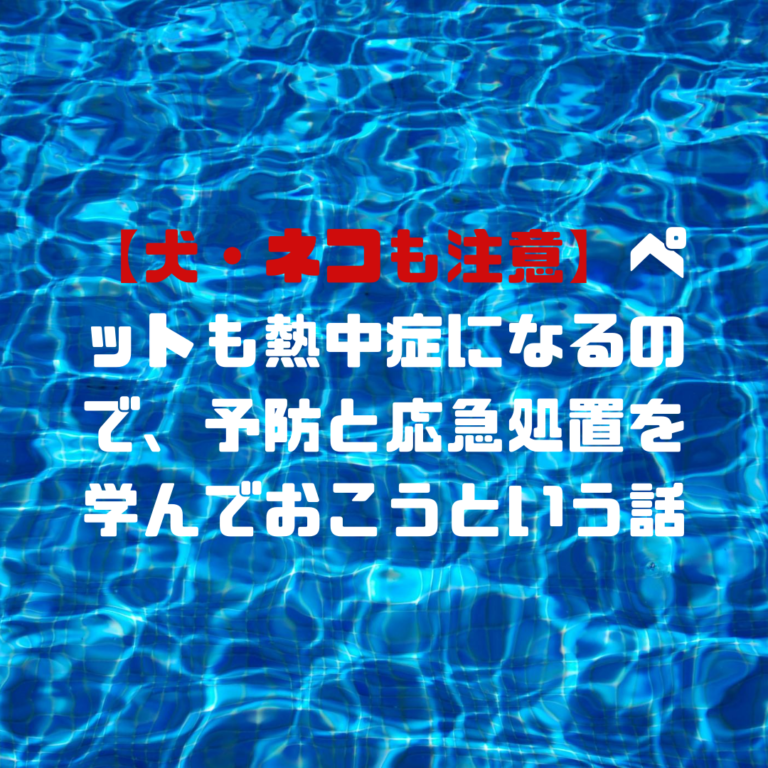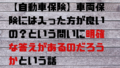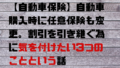つい先日、炎天下の昼下がりに自動車で移動中、男性のお年寄りが犬の散歩をしている姿を見かけました。時間は13時30前後だったと記憶しています。その方自身もタオルで汗を拭きながら歩いていましたが、ハアハアと舌を出し、引きずられるように歩くわんちゃんにも目を奪われました。
熱中症とか大丈夫なのだろうか?と思いましたが、そのまま通り過ぎてしまったので、その2人(1人と1匹)の無事を願うばかりです。そこで今回は、ペットと過ごしている方に、ペットの熱中症予防と万が一ペットが体調を崩した際の対策をお伝えしたいと思います。皆様のペットライフのお役に立てれば幸いです。
↓↓かわいいペット用品大集合!新規会員登録ですぐに使える500円クーポンプレゼント↓↓

日本気象協会の熱中症予防対策の取り組み
こんにちは。当ブログへ訪問頂きありがとうございます。
連日、日本各地で体温をこえるような気温を記録していますが、皆様におかれましては、くれぐれも熱中症等にお気をつけていただきたいと思います。
ペットとともに過ごしている皆様には、ご自身の熱中症に加え、ペットの熱中症についても気になるところではないかなあと思います。
私自身、犬を飼っている身、気になり調べてみて発見した、一般社団法人日本気象協会が推進・作成している、
というページをご紹介致します。

熱中症ゼロへ みんなの力で熱中症をゼロにしよう
このホームページのトップページに
「熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指して、一般財団法人 日本気象協会が推進するプロジェクトです。
熱中症は、正しく対策をおこなうことで防げます。私達は、熱中症の発生に大きな影響を与える気象情報の発信を核により積極的に熱中症対策を呼びかけていきます。」
とあり、そのコンセプトのもと、熱中症を学ぶ・専門家からのアドバイス等が学べるサイトになっています。その中に、ペットの熱中症対策についての項目があります。
犬や猫を飼っている人
「熱中症ゼロへ みんなの力で熱中症をゼロにしよう」の中に、「犬や猫を飼っている人」というページがあります。その中に、ペットの熱中症対策のことが書かれています。その症状はまれに猫にも見られるようですが圧倒的に犬に発症することが多いようです。
熱中症の症状
では、まずその症状ですが、ページ内にはこのように記載してあります。
【初期症状】
パンティング(ハアハアと激しい呼吸)、よだれ、粘膜(歯肉や舌、結膜など)の充血やうっ血、頻脈などが見られます。
可能な状況であればなるべく体温測定をしてください。体温測定は深部体温の測定が大切ですので直腸(肛門)で測定すると良いでしょう。40℃を超える場合には熱中症の疑いが濃厚です。
【重篤化した場合】
虚脱(ぐったりとして意識がない)、嘔吐下痢、ふるえ、意識消失、けいれん発作、ARDS(急性呼吸促迫症候群)などを生じる場合もあります。
さらに、これらに付随してDIC(播種性血管内凝固症候群)を発生することも多く、この場合高い確率で死に至ります。
散歩中に舌を出して激しくハアハアという事がありますよね。そのようなときは少し気にしてみてあげる必要があるかもしれません。
熱中症の予防・対策
予防・対策については以下の通り。
ペットを高温の環境に置かないことが最大の予防となります。
【屋外】
暑い季節の外出時刻には注意が必要です。気温も大切ですが、地面から近いところを歩く犬は気温以上に高温の環境下に晒されているということを忘れてはなりません。朝夕涼しく感じても、お散歩の際にはアスファルトをさわって確かめてみましょう。
暑い時期に外出しなければならない場合には、こまめな給水を心がけ、時には体表に水道水をかけ流し、さらに風を送りなどの気化熱を利用した簡易的な体幹冷却法(*)を取り入れることも良いでしょう。
* 体幹冷却法 頚部(喉から首にかけて)から体幹(胸そして内腿を含めたお腹全域)に水道水をかけたり、水分を多く含んだタオルをかけて団扇であおぐなど。
【室内】
室内では風通しを良くしておくことや、ペットが自由に居場所を選択できるようにしておくことも重要です。暑い時期の室内の温度は26℃以下で維持するようにします。
【車内】
外気温が25℃を超えるような環境下では締め切った車の中に置くことは避けましょう(活動的な犬や興奮しやすい犬の場合には、さらに低い気温でも熱中症のリスクがあります)。
また、犬や猫がいつでも自由に飲水できるようにしておきましょう。
屋外・屋内・車内、状況別に解説してくれています。中でも、屋外については丁寧に解説してあります。朝夕のすずしく感じる時間帯でもアスファルトの熱を確認する、というのは意外と忘れがちかもしれませんので注意が必要かと思います。
応急処置のポイント
万が一発症が疑われた場合の対応については以下のように解説してくれています。
熱中症に対する治療の遅延は死に至るため、熱中症が疑われたら早急に治療をすることが大切です(症状の出現から90分以内)。
全身に常温の水道水をかけて冷却したり、水道水で濡らしたタオルなどで包み、涼しい場所で風を送り体幹冷却に努め、直ちに動物病院を受診してください。熱中症は重症化すると死に至る致死率の高い病気ですが、応急処置の際に、早く体温を下げようとして冷水や氷、アイスバッグを用いて急激に冷却すると、抹消血管が収縮し、温度の高い血液が各臓器に循環します。そうなると熱が発散しにくくなり、深部体温が下がらずに高体温による各臓器への障害が促進されて逆効果となるため、注意が必要です。
愛犬(愛猫)に熱中症の症状が見られた場合、慌ててしまい、「とにかく冷してあげないと!!」とアイスバッグ等で冷やそうとするかもしれませんが、その行為はNGとありますので注意が必要ですね。
熱中症に特に注意が必要な犬種・猫種
最後にどのような犬種・描種が特に注意が必要なのかも記載がありましたので転記いたします。
犬ではフレンチ・ブルドッグ、パグ、シーズーなど、猫ではペルシャ、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなどの短頭種は特に熱中症に陥りやすい種です。肥満である場合には犬猫共に注意が必要です。その他、呼吸状態の悪化を招きやすく、体温上昇に直結し、かつ脱水状態を引き起こすような病気を患っている場合も、熱中症の注意が必要です。例えば、
・ 循環器疾患(心臓弁膜症など)
・ 慢性呼吸器疾患
・ 内分泌疾患(副腎皮質機能亢進症など)
・ 脳神経系疾患(原因は様々ですがけいれん発作を伴う病気、四肢麻痺を伴う病気)
・ 腎疾患(慢性腎臓病など)
などが該当します。
さらに、昨今では高温環境ではないにもかかわらず熱中症を引き起こす病気があります。認知機能不全症候群に陥っている高齢動物です。
認知機能不全症候群の動物(主に犬)は、水を飲む場所が認識できない、家具の隙間など閉所から脱出できない、あるいは長時間吠え続ける等の症状が見られますが、これらの場合、体温上昇ならびに脱水症状を引き起こし易く、熱中症の状態に陥ってしまうこともあるので、非常に注意が必要です。
犬種・描種に加え現症の有無も熱中症発症に影響を与えるようなので注意が必要ですね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、ペットの熱中症について確認してみたところ、とても分かりやすいホームページがありましたのでご紹介をさせていただきました。冒頭のお年寄りのように、お昼の散歩は自分の為にもペットのためにも避けた方が良い気がしますね。
我々自身も当然ですが、ペットも熱中症には十分ご注意いただきたいと思います。
皆様のかわいいペットの健康推進の一助になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※出典:熱中症ゼロへ みんなの力で熱中症をゼロにしよう